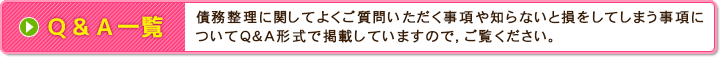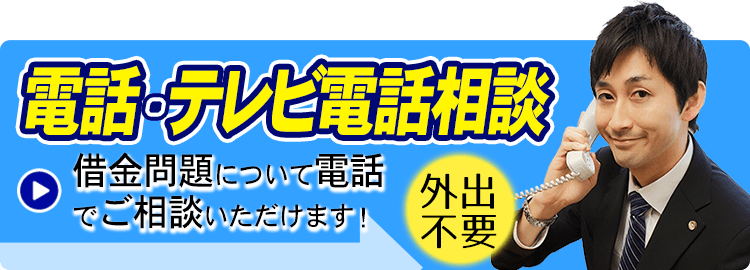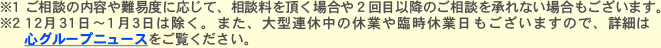「債務整理」に関するお役立ち情報
借金で強制執行を受けた場合の対応方法
1 強制執行に対する現実的な対応策は債務整理
債務の返済ができない状態が続き、貸金業者等が訴訟提起や支払督促の申立てをすると、最終的には強制執行によって債務者の方の財産が差し押さえられることがあります。
預貯金口座や給与が差し押さえられてしまうと、日常生活にも支障が生じます。
この状況を放置しても状況は悪化する一方ですので、現実的には債務整理をしないと問題は解決しないと考えられます。
以下、強制執行に至るまでの経緯と、債務整理の方法(任意整理、個人再生、自己破産)について説明します。
2 強制執行に至るまでの経緯
借金等の返済を滞らせてしまうと、一般的には、まず貸金業者等から電話や手紙で連絡がなされます。
この時点で貸金業者等へ連絡をしないでいると、貸金業者等が債権回収のために訴訟提起や支払督促の申立てをすることがあります。
訴訟や支払督促への対応をしないでいた場合、判決や仮執行宣言付支払督促が確定し、強制執行が可能となります。
返済ができない状態を放置していると、最終的に預貯金口座や給与の差押えなどの強制執行に至ってしまうのです。
返済が困難になった場合には、できる限り早く弁護士に相談し、債務整理を行う必要があります。
3 任意整理による対応
任意整理は、弁護士が個別に貸金業者等と直接交渉を行い、基本的には残債務の元金(経過利息、遅延損害金の合計額)を3~5年間程度で分割して返済できるようにする手法です。
債務額が比較的少なく、任意整理後の返済原資の確保ができる場合に有効な手段です。
強制執行がなされている状態であっても、実務においては、貸金業者等が任意整理に応じることはあります。
4 個人再生による対応
個人再生は、裁判所を通じて債務総額を大幅に減額し、減額後の債務を原則として3年で分割返済できるようになる手続きです。
強制執行を受けてしまっている場合に、個人再生手続き開始決定がなされたら、強制執行を決定した執行裁判所に対して上申し、強制執行を中止してもらうことになります。
ただし、給与が差し押さえられている場合、原則として再生計画の認可決定が確定するまで、給与の4分の3を超える額の支払いは留保されたままとなり、残りの分は会社が保管するため、手元に入りません。
5 自己破産
自己破産も裁判所を介した債務整理の方法であり、一部の例外を除く債務の返済義務を免れることができる手続きです。
他の債務整理の方法では解決ができない場合には、自己破産を選択することになります。
自己破産の申立てをした後、同時廃止事件になった場合、破産手続開始決定がなされたら、強制執行をしている決定した執行裁判所に対して上申し、強制執行を中止してもらうことになります。
ただし、給与が差し押さえられている場合、免責許可決定が確定するまで、給与の4分の3を超える額の支払いは留保されたままとなり、残りの給与は会社が保管するため、手元に入りません。管財事件になった場合、破産手続開始決定後、破産管財人が執行裁判所に上申することで、その後の給与は受け取ることができるようになります。
また、勤務先に給与がプールされていた場合は、自由財産の拡張が認められると、その分についても受け取ることができるようになります。
公務員の債務整理 借金が雪だるま式に増えてしまった場合の対応